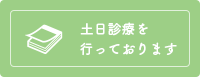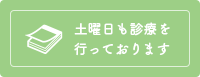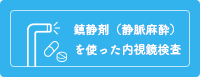このような体験はないでしょうか。
- 手の汚れが気になり何十回も手洗いをしてしまう
- 出かけるときに、鍵をかけたか・戸締りしたかを何度も確認してしまう・確認しすぎて待ち合わせや仕事がずれこんでしまう
- 「やりすぎ」と分かっていても止められない
上記のようなことで日常生活に支障をきたしている場合、強迫性障害の診断がつくかもしれません。
自分の意思とは関係なく、ある考えやイメージが頭に浮かんで離れなくなり(強迫観念)、そこで生まれた不安を改善するために同じ行動を何度も繰り返すこと(強迫行為)で日常生活に支障が出てしまう不安障害のひとつです。
他には、誰かに危害を加えたかもしれない、という加害強迫や、自分の頑ななルーティンがあり、そこから外れると大変なことが起こるのではないかと不安で同じ手順から離れられない(儀式行為)といったものもあります。また、机のものの置き方が常に同じでないとダメと言う人もいます。
これらに振り回されると、日常生活に様々な支障を生じるようになってしまいます(水道代が莫大、仕事の締め切りに間に合わない、など)。
① 薬物療法
強迫性障害も不安の病気の一つですので、パニック障害や社交不安障害と同様に抗うつ薬の一種であるSSRI(セロトニン再取り込み阻害薬)を使用する事が多いです。また、適宜抗不安薬を併用することもあります。
強迫性障害では、強迫観念から不安になると、不安を解消するために手を洗う/確認するのですが、これらによって、不安は一瞬改善するのですが、これはまた次の不安を引き起こすことになり、また手を洗う/確認をして一瞬安心してはまた不安になる、という無限のループにはまる事になります。非薬物療法では、このループを断ち切ることが必要になります。例えば「自分が汚いと思っているものを触っても手を洗わない」「戸締りが気になってもいったん外出したら家に引き返さない」など、今までとは逆の行動を取っていく、などです。最初は非常に不快で不安なものですが、これを繰り返すことで、思っていたほど大事に至らなかった、不安だったけど大丈夫だった、という感覚が得られるようになり、徐々にこのループが緩んできて、楽になっていきます。
強迫性障害の非薬物療法は、非常に苦痛を伴うと思われるので、薬物療法とうまく組み合わせて取り組んでみることをお勧めします。